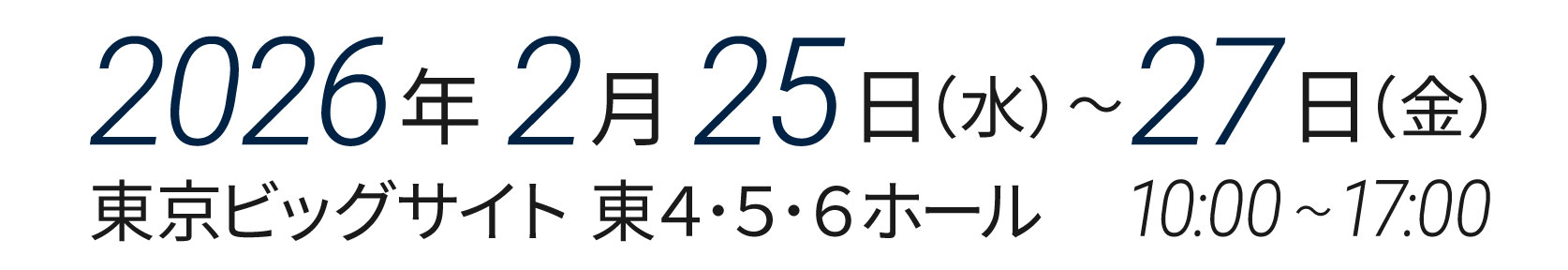特集【アンチ・ドーピング(AD)】 国内 ・ 海外分析機関の活用進む
(公財)日本スポーツ協会 スポーツ医・科学委員会が2024年3月に発表した『スポーツ現場におけるサプリメントの利用状況と活用コンセンサスの作成』によると、アスリート439人中、「サプリメントを使用している」人は、228人と半数以上だった。また、「サプリメントが必要な状況」の質問では、回答が多い順に「運動やスポーツをする時」が112人、「筋力をアップさせたい時」が106人、「疲れた時」が98人だった。今や、サプリメントはアスリートのパフォーマンス向上にとって必須のツールとなっている。一方で、アスリートがサプリメントを使用する上で、最も重要な点がドーピング検査に抵触しないかという点だ。前述の調査では、「アンチ・ドーピングを意識している」と回答した人数は329人で、7割以上のアスリートがドーピングに注意を払っていることがうかがえる。
日本人アスリートの2023年度のドーピング規則違反は5人で海外の選手と比べ圧倒的に少ない。背景には、アスリートや指導者のモラルの表れと同時に、「よくわからないサプリメントなら摂らないでおこう」という思考がある。ドーピング違反は、たとえAD認証を取得した製品であろうと、選手やその関係者の責任が問われることになるからだ。しかし、サプリメントを避けることによるパフォーマンス向上や疲労回復の機会損失も潜んでいる。スポーツ栄養学会の鈴木志保子理事長は、「食事だけでは必要な栄養素を十分摂取できないアスリートにとって、勝つためには、サプリメントで補わないといけないケースがある。同時に、ドーピング対策は自身を守るための行動で、専門家に相談することやアンチ・ドーピング(AD)認証は、アスリートにとって安心の判断材料となる」と話す。実際、スポーツファーマシストや管理栄養士のもとには、大会前には特に、「このサプリメントは安全か」「どんな栄養素を取ればいいか」などの相談が寄せられるという。こうした相談に対し、彼らが安全基準のひとつの判断材料としているのが、「アンチ・ドーピング検査」で安全性が担保された製品、AD認証製品になるという。
ドーピング成分の検査において、日本含む各国では、世界アンチ・ドーピング機構(WADA)が公表するドーピング禁止物質を参考に、ドーピング成分の分析・検査を行う専門機関を設けている。英国では、スポーツをドーピングから保護する責任を負う公的な組織であるUKADが管轄し、「Informed Choice(以降IC)」(LGC社)を推奨している。ICは、世界で最も歴史のあるアンチ・ドーピング認証機関として知られ、各国でドーピング検査・認証業務を行っている。米国では、アンチ・ドーピング組織であるUSADAが管轄し、NSFスポーツ認証を推奨している。他にも米国には、国際オリンピック委員会医学委員会のメンバーで、薬物検査のエキスパートのドン・H・カトリン氏が立ち上げた禁止薬物検査機関であるBSCG社のCERTIFIED DRUG FREE(BSCG)などがある。
日本でも、2019年までは日本アンチ・ドーピング機構(JADA)が認証業務を行っていたが、2019年に認証業務を終了。現在、日本でAD認証を取得する場合は、LGC社のIC、NSFによるNSF SPORTS、BSCG社のBSCGなどの選択肢があり、ICおよびBSCGは、日本にも窓口が存在する。また、認証は行っていないが、日本でISO17025基準のドーピング分析を行う機関は、日本分析センターとイルホープがある。どちらもJADAが公開する国際基準である違反成分範囲の分析を行い、海外の認証機関と同レベルの検査機械で分析を行っている。2機関共に、認証マークではないが、検査済のマークを製品に付与するサービスを実施。海外との煩雑なやり取りがなく、精度の高い国内完結型の分析が評判となり、問合わせ件数も分析依頼数も増えている。ただ、日本分析センターは、2025年3月31日をもってドーピング成分の分析事業を終了することを発表。4月以降、国内でドーピング成分の分析ができる機関はイルホープ1社のみとなる。つづく
詳しくは健康産業新聞1808号(2025.3.19)で
健康産業新聞の定期購読申込はこちら