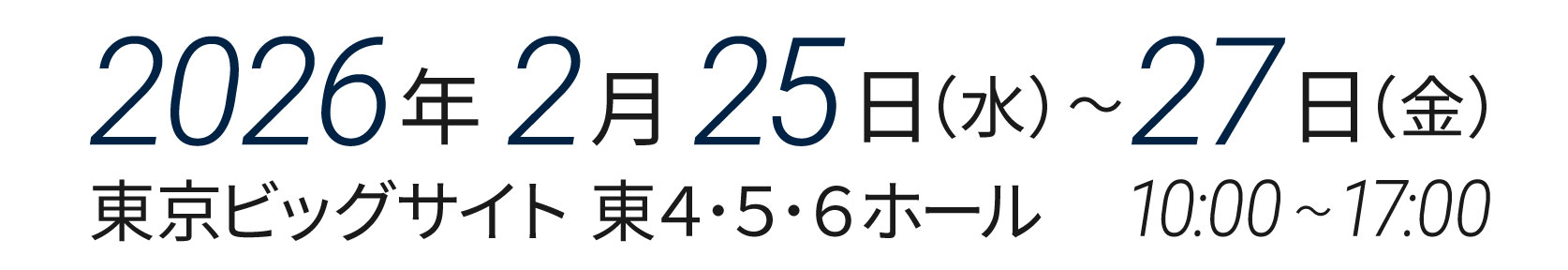食品産業センター、日本版栄養プロファイリングモデル開発
食品産業センターは2月19日、食品を栄養組成に従って分類・ランク付けする「日本版栄養プロファイリングモデル(NPモデル)」についてのセミナーを開催、NPモデルの紹介や活用方法について説明した。冒頭の挨拶で農林水産省大臣官房新事業・食品産業部新事業国際グループ長の飯田明子氏は、栄養プロファイリングモデルの料理版は他国にはない新しい考え方と言及。農水省としては、実際に活用されることで政策上の効果が発揮されるとし、企業にセミナーを通して理解を深め、積極的な発言をすることを呼びかけた。
医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所食品保健機能研究センター食品分析・表示研究室室長の竹林純氏は、NPモデルの概要と「加工食品版」について説明。NPモデルは日本の食文化や栄養課題を踏まえて、特定の栄養素等の含有量で総合的に食品の栄養化を評価できる仕組みの開発を目指し、スコアリングモデルでの「加工食品版」に加え、世界初となる「料理版」を開発したと紹介した。「加工食品版」は、食品の100g当たりに含まれる、栄養成分表示の義務項目である熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムと栄養成分表示の推奨項目である飽和脂肪酸、食物繊維、zた糖類、野菜等の重量の割合から栄養成分の量の多い、少ないに基づいて最終スコアを計算。最終スコアから栄養化に基づく食品のランク付けを行うという。つづく
詳しくは健康産業新聞1807号(2025.3.5)で
健康産業新聞の定期購読申込はこちら