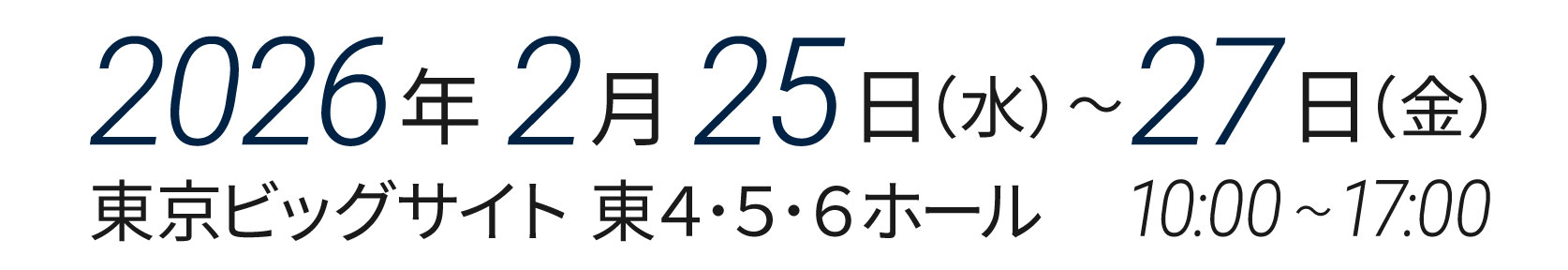別冊【腸内細菌】 第3の領域「ポストバイオティクス」に高い関心
近年、次世代シーケンサーの登場などにより、腸内細菌叢がゲノムレベルで解析されるようになった。メタボローム解析などの解析技術が飛躍的に進歩したことで、腸内細菌の多様性が把握できるようになり、同時に疾患との関連性もわかってきた。腸内細菌のバランスが崩れると様々な疾患リスクが高まるため、腸内細菌を良好に保つ重要性がますます認識されている。このことから、「プロバイオティクス(生菌)」や、腸内常在菌のエサとなる「プレバイオティクス」、さらに最近では菌が代謝し生成する短鎖脂肪酸などの物質を指す「ポストバイオティクス」が有効であるとして年々関心が寄せられている。また、生菌を加熱殺菌した死菌体原料について、最近では「消費者に健康上の利益をもたらす不活性化微生物細胞(非生存性)」と定義される「パラプロバイオティクス」として差別化され、こちらも利用が拡大している。
近年よく耳にするようになったのが「ポストバイオティクス」。生物に関連するという意味の「biotic」と、生命後を意味する「post」が語源とされており、腸内細菌が作り出す短鎖脂肪をはじめとした有用な代謝産物を指す。そして加熱殺菌処理などにより不活化した微生物(死菌体)を指す言葉として登場したのが「パラプロバイオティクス」だ。パラプロバイオティクスは適応免疫系と自然免疫系を調節する能力を持ち、抗炎症、抗増殖、抗酸化特性を示し、病原体に対して拮抗効果を発揮するのが特長。安全性が向上し、技術的および実用的な利点が保証され、免疫力が弱い人や高齢者に適した製品にも使用できるのが利点とされている。つづく
詳しくは健康産業新聞1806号別冊『腸内細菌』(2025.2.19)で
健康産業新聞の定期購読申込はこちら