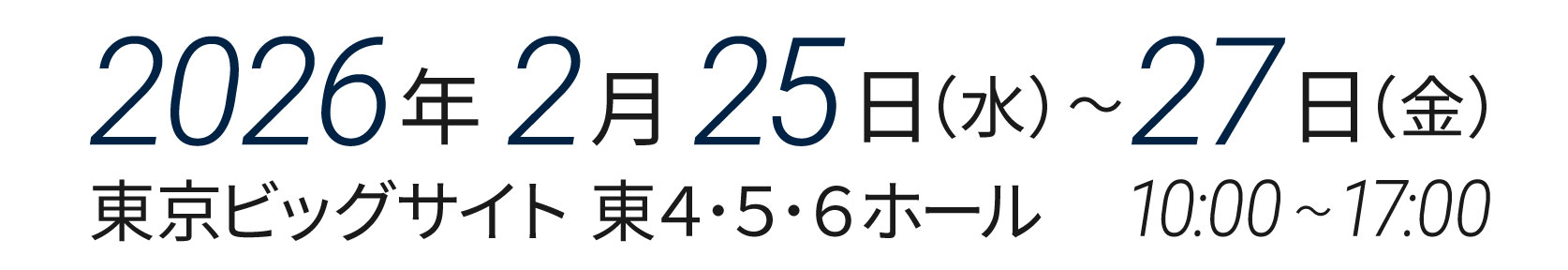ファンクショナルフード学会、都内で学術集会
ファンクショナルフード学会は2月8~9日の2日間、城西大学東京紀尾井町キャンパスで「第21回ファンクショナルフード学会学術集会」を開催した。今回のテーマは「機能性食品開発の現状と新展開」。大会長の城西大学薬学部医療栄養学科の和田政裕氏は冒頭の挨拶で、「食品機能の新しいデータを発表する場として、どのように研究が進んでいるのか、交流の場として活発な議論をして頂きたい」と述べた。
初日の特別講演では、城西大学薬学部薬科学科の片倉賢紀氏が、「機能性食品としての多価不飽和脂肪酸の現状と今後の可能性」と題して講演。多価不飽和脂肪酸およびその代謝物による神経幹細胞の分化制御機構と、モデルラットを用いた腎不全の予防・進行抑制効果について紹介した。DHAは認知機能、EPAにはうつ病に効果があることが報告されており、海馬でニューロンがどれだけ増えたかを確認すべく、神経幹細胞を用いた試験を実施し、細胞内のシグナル伝達がω-3多価不飽和脂肪酸誘導性神経発生に関与している旨を概説した。また、慢性腎不全を予防する可能性があるメカニズムの1つとして、DHAを含む食事が腎臓の酸化ストレスと線維化の両方に影響を及ぼし、腎不全の進行を抑制できるとした。DHA/EPAの供給源となる世界的な漁獲量の減少についても触れ、代替脂資源の確保の必要性についても述べた。
2日目のランチョンセミナーでは、(公財)東洋食品研究所・新谷知也氏が、「グルコサミンの新しい機能性と社会実装」と題して講演した。同氏は、グルコサミンのオートファジーの誘導を介した寿命延長や腸内環境に対する影響など、これまでの研究成果を紹介した。グルコサミン摂取により、酪酸菌Anaerostipesが増加し、長寿に寄与する可能性があると言及。グルコサミンサプリメントを使用した便通改善を目的とした臨床研究を開始することを報告した。今後、腸内細菌叢改善を目的としたランダム化試験も計画中だという。さらに、米国国立老化研究所が実施するアンチエイジング物質の検証プログラムに採択され、米国3施設でグルコサミンの長期投与試験を実施するという。同氏は、社会実装に向けて、「エビデンスを積み重ねて、オートファジー認証マークの活用や新たなヘルスクレームの機能性表示食品開発に繋げたい。もっとグルコサミンが注目される素材になって欲しい」と述べた。つづく
詳しくは健康産業新聞1806号(2025.2.19)で
健康産業新聞の定期購読申込はこちら