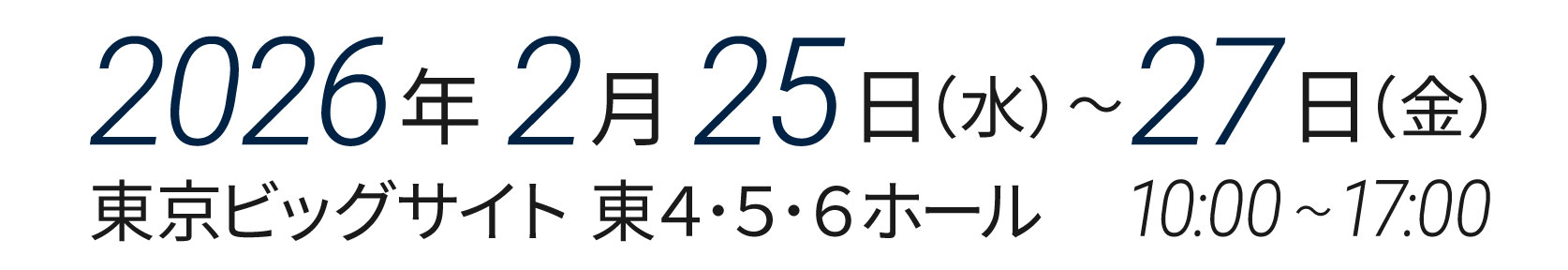ZOOM UP【殺菌技術】 原料の特性を引き出す殺菌ノウハウ
総菜や社食、弁当などの食中毒事件は毎年発生しており、生鮮や加工食品において、異物混入や残留農薬、微生物汚染など食品の品質・安全管理対策は不可欠だ。ノロウイルスによる食中毒事件も相次いでおり、食の品質・安全管理対策には一段と厳しい目が向けられている。健康食品原料には、1g当たり数十~数千万個の大腸菌群・陽性が一般的で、品質・安全性の観点から殺菌が重要視される。開発においては、素材の特性に応じて機能性を担保するための品質保持・改善のためにも殺菌は欠かせない工程だ。健康食品原料には、植物系や動物系の天然由来原料が多く、原料特性に応じて有用成分や色調、味、香りなどの特性を損なわない殺菌技術が要求される。殺菌の需要が増えている原料は、大麦若葉、アシタバ、モリンガ葉などの青汁用素材をはじめ、ウコン、ショウガ、田七人参など漢方素材、イチョウ葉、キノコ類、スッポンなど幅広く、これらの粉体全般で殺菌依頼が増えている。
粉体殺菌には、加熱殺菌、薬剤殺菌、紫外線殺菌などの方式がある。数ある殺菌方式の中でも、加熱殺菌は、殺菌能力・原料への影響・コストの面で評価されている。加熱殺菌はさらに、低温殺菌(蒸気・熱湯)、高温殺菌(過熱蒸気、煮沸)、高周波、マイクロ波、赤外線、遠赤外線など様々な方法に分類され、原料本来の「色調」「香り」「味」を損なわないよう、原料の特性にあわせた殺菌方法が要求される。健康食品原料の殺菌工程で最もポピュラーな殺菌法は、殺菌機に原料投入した際に発生する結露水膜(飽和水蒸気)に熱エネルギーを加える高圧蒸気殺菌法だ。原料特性に応じて使用する殺菌機を分けることで、“色調劣化”や“成分劣化”を抑えることができる。また、短時間で耐熱性芽胞菌も死滅させることが可能であるほか、「殺菌対象となる原料を必要以上に濡らさない」「過熱水蒸気による殺菌のため、安全性が高い」「短時間・無酸素状態での殺菌のため、有効成分の損失や酸化が少ない」といったメリットが評価されている。殺菌受託各社では、素材の色や風味を残したまま殺菌するために、色調劣化や成分劣化を抑制するだけでなく、素材の美味しさを損なわないよう、原料特性に応じた最適な殺菌・滅菌技術のノウハウで、様々なニーズに対応している。つづく
詳しくは健康産業新聞1805号(2025.2.5)で
健康産業新聞の定期購読申込はこちら