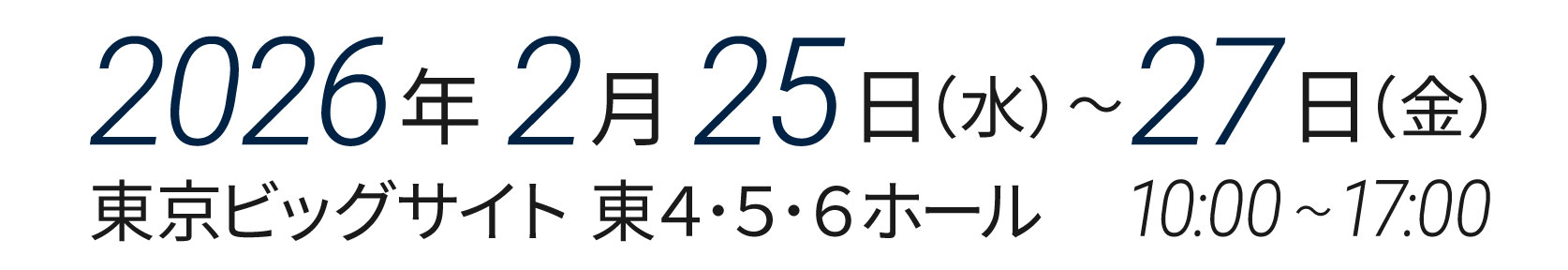特集【医家向けサプリメント】 自由診療クリニック1万軒突破、 3年で13%増
厚生労働省の統計によると、令和5年の19床以下の医療機関は、全国で10万4,894軒あり、その内、自由診療のみを行うクリニックは1万428軒となった。同調査は、3年に1回行われており、前回調査(令和2年)の9,263軒より1割程度増加している。前々回の調査でも同等の伸び率を示しており、自由診療クリニックが年々増加している傾向がうかがえる。同省が発表した令和4年の国民概算医療費は、前年比4.0%増の46兆円。医療費は過去最高額を記録し、保険診療の逼迫が危惧されている。特に高齢者の医療費拡大が課題となる中、認知症やフレイル予防に対する啓発活動を強めている。医療機関でも患者の健康長寿を後押しすべく、運動・食事習慣の指導などのフレイル対策を強化している。
医療機関において、かつては異端とされていた食事や栄養、サプリメント療法は、臨床数も増え、様々な診療科で利用されるようになった。実際、保険診療でカバーできない治療やエイジングケアを行うクリニックでサプリメントを扱う件数が増えている。30年以上前からホリスティック療法を行う帯津良一医師は、「薬では治せない病気がある」という考えの下、自由診療でホリスティック療法やサプリメント療法を行っている。帯津医師は、ナットウキナーゼのサプリメントを自身でも摂取しており、自身が経営する帯津三敬病院でも販売している。栄養療法を行うみぞぐちクリニックの溝口徹医師は20年前、家族の原因不明の病が、栄養療法で回復に向かったことをきっかけに、保険診療から自由診療に変えた。溝口医師は、現在若手の医師に向けて講演を行い今後の栄養療法の可能性について語っている。美容クリニックを運営する藤本幸弘医師は、エイジングケアにおいてレーザー治療をメインとする一方、病気にならないための『ディフェンシブ栄養学』と、より健康で若くなりたいと思う人のための『オフェンシブ栄養学』を提唱。同氏は、「エイジングケアにおいて抗酸化、テストステロン、免疫力の役割が大きい」と話す。そこでビタミンDや亜鉛が含有された食事やサプリメントなどを提案している。
一般流通のサプリメントと医家向けサプリメントの違いは、有効性、安全性における臨床試験の数、論文発表の多さなどに差異が見られる。医師による体感や医師のネットワークでの紹介も採用になるケースがあるという。国内外にネットワークを有する医師の紹介によって台湾やシンガポールのクリニックで扱って貰えるようになったなどの声も聞かれる。なかでも各学会での研究発表や学術論文の投稿は、医師が採用する要になっている。医家向けサプリメーカーの中には、200報以上の査読付き論文としてアクセプトされているケースも少なくない。つづく
詳しくは健康産業新聞1804号(2025.1.15)で
健康産業新聞の定期購読申込はこちら