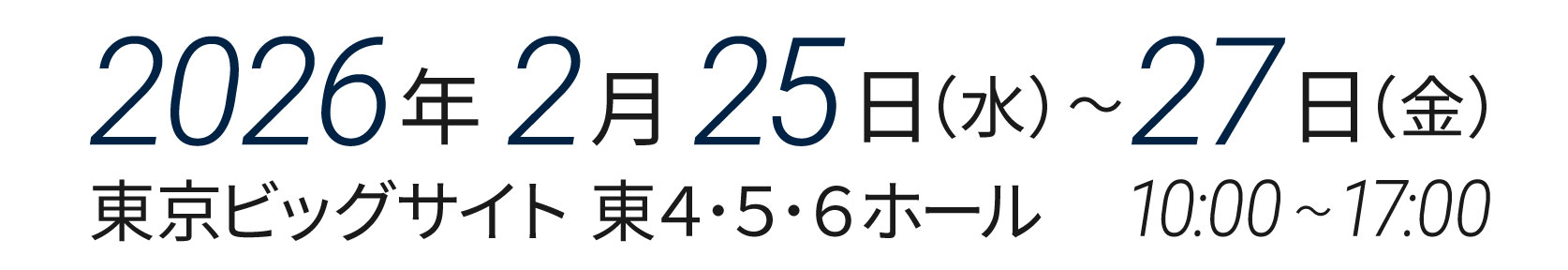【行政動向】 改正「機能性表示」制度始動
◆健康被害の報告を義務化
消費者庁は24年8月23日、機能性表示食品に関する食品表示基準の一部を改正する内閣府令を公布。厚生労働省は同日、食品衛生法施行規則の一部を改正する省令を公布した。紅麹問題を受けた「機能性表示食品を巡る検討会」の報告書、「紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合」がまとめた対応方針を踏まえた制度改正の大枠が確定した。改正の大きな柱は、「健康被害の報告義務化」「サプリ剤型のGMP要件化」「パッケージに記載する表示の見直し」―― の3点だ。
「健康被害の報告義務化」は24年9月1日に施行。医師が診断した症例で、因果関係が否定できないもの(不明なものも含む)が情報提供の対象。同じ所見の症例が短期間で複数発生した場合と、重篤事例が起きた場合、情報提供を行うこととする。重篤事例は1例でも報告する必要がある。報告までに2ヵ月を要した紅麹問題を踏まえて、提供期限も設定。健康被害を診断した医療機関名を知った日から15日以内に報告することを求める。
「サプリ剤型のGMP要件化」に関しては、24年8月30日に「機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準」(GMP基準)を告示した。届出者に対し、告示対象となる原材料について、「製造者等が作成する製品標準書に記載した規格に適合したものが供給されることを確保しなければならない」ことを規定。このほか「製品標準書等の備付け等」「原材料の製造管理及び品質管理」「バリデーションの実施等」などを盛り込んでいる。焦点となるのは、告示対象となる「錠剤、カプセル剤等食品」の範囲。これについては今年度中に示される見通しだ。なおGMP要件化に関しては、準備に時間が必要なことを踏まえ、2026年8月31日までを経過措置期間とする。
「パッケージに記載する表示の見直し」は、「機能性表示食品」の文字を枠で囲み、主要面の上部に表示、その近接する箇所に「届出番号」を記載することで統一する。さらに、研究レビューで評価した場合は、「成分が有する機能性」であることを明確にすることを規定。例えば、「〇〇し、△△する」と切り取らず、「□□(成分)には〇〇し、△△する機能があることが報告されています」といった表示にする必要がある。包材変更が必要となるため、表示の見直しに関しても2026年8月31日までを経過措置期間とする。さらに今年4月から、新規成分を慎重に確認する「120日ルール」を導入。従来は60日としている確認期間を倍の120日にして、確認に時間を要する成分について、専門家からの意見聴取を行う。適用される要件についても、今年度中に示す方針。
◆微生物等原材料で新指針
紅麹問題を受けた対応はほかにもある。現在、錠剤・カプセル剤等の形状の食品については、「『錠剤、カプセル剤等食品の原材料の安全性に関する自主点検及び製品設計に関する指針(ガイドライン)』及び『錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理(GMP)に関する指針(ガイドライン)について』」(令和6年通知)が示されており、安全性確保に関する自主的な取り組みを推奨している。紅麹問題を受けた消費者庁の「機能性表示食品を巡る検討会」は5月にまとめた報告書で、「菌体のような特殊な原材料を用いる場合のリスク管理に関する科学的知見の集積」の検討の必要性を指摘した。国立医薬品食品衛生研究所に研究班が設置され、「微生物等(藻類を含む)の培養または発酵工程を経て生産される原材料」(微生物等関連原材料)のリスク管理について検討。これらの原材料を用いた食品に対し、「製造管理・品質管理により一層の注意が必要」とされたことを受けて、前述の「令和6年通知」を一部改正することとした。
つづく
詳しくは健康産業新聞1803号別冊「新年特別号」(2025.1.1)で
健康産業新聞の定期購読申込はこちら