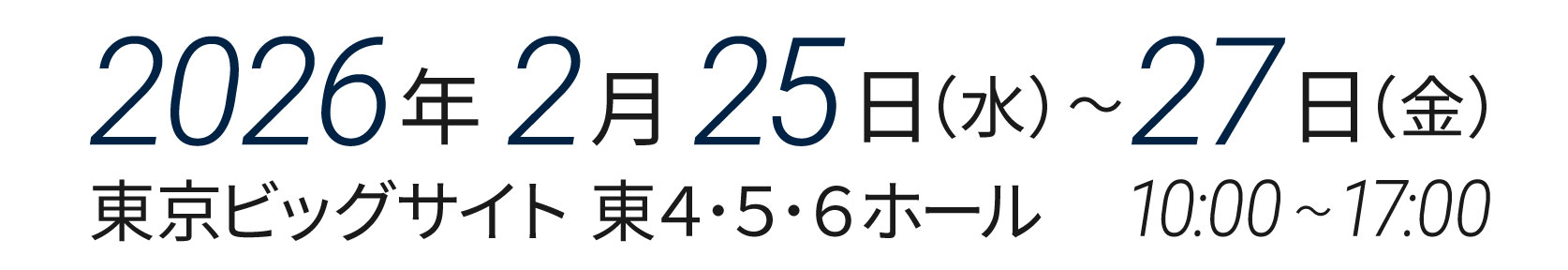特集【ミネラル】 食事摂取基準改定、高まるカルシウム摂取の重要性
厚生労働省は2024年10月、「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会の報告書を公開した。鉄について、従来の2020年版では耐容上限量(成人男性では50mg/日、成人女性では40mg/日)が設定されていたが、今回の改訂では耐容上限量の設定は見合わせることに。食事からの過剰摂取で健康障害を引き起こす明確な根拠が研究論文などで見当たらないことを理由とした。一般的な食事等に由来する鉄が過剰に臓器に蓄積する事例には、ヘプシジンの鉄吸収制御に関わる遺伝子等の異常が指摘されている。一方、遺伝子の異常がない場合、食事からの鉄摂取が多くなっても、ヘプシジンによる調節で鉄の吸収量は正常な範囲に維持されるとの報告があるとしている。このほか、月経のある日本人女性における鉄欠乏の最大の要因は、月経に伴う鉄損失であって、鉄摂取量とは関連がないという報告もあるため、「推奨量を超えて鉄を摂取しても必ずしも貧血の予防には繋がらない可能性がある」とし、推奨量を大きく超える鉄の摂取は、貧血の治療等を目的とした場合を除き控えるべきとした。
2025年版では、「生活機能の維持・向上に係る疾患等」として骨粗鬆症が取り上げられている。骨粗鬆症予防のためのカルシウムの重要性が述べられており、「若年者に対しては最大骨量の最大化を」「閉経期女性に対しては閉経後骨量減少を、 男性に対しては加齢による骨密度低下を、それぞれ最小化することを目指す必要がある」旨を明記した。若年者への介入について、長期にわたる追跡研究はないものの、「若年期に高い骨密度を獲得しておくと、後年になって骨密度の低下があっても、骨粗鬆症の発症や骨折閾値への到達を遅らせることができ、骨粗鬆症の発症予防に資すると考えられる」とした。さらに、日本人女性における年齢別骨密度に関する調査を例示し、「思春期に骨密度は高まり、およそ20歳で最大値に達し、40歳代前半までそれが持続した後に閉経前頃から低下することが示されている。最大骨量を最大化するための最も効果的な介入時期は少なくとも18歳以前にあるといえる」とし、若年期におけるカルシウム摂取の重要性を説いている。カルシウムは令和5年国民健康・栄養調査で示す数値との比較でも、充足率の低さが目立っている。30~49歳男性を例にとると、食事摂取基準2025の推奨量750mgに対し、国民健康・栄養調査では443mgに。307mg足りない状況となっている。つづく
詳しくは健康産業新聞1803号(2025.1.1)で
健康産業新聞の定期購読申込はこちら