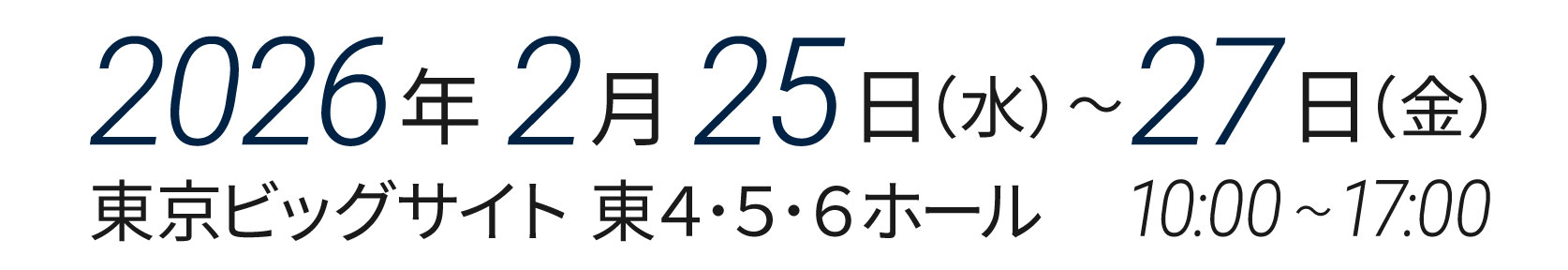【話題追跡】 ブランドの高付加価値化、SDGs… 広がるブルーカーボンプロジェクト
陸地にある森林などが吸収・貯留した炭素を「グリーンカーボン」というのに対して、「ブルーカーボン」とは、海藻藻場など海洋生態系が光合成によりCO2を取り込み、海底に貯留する有機炭素を指し、昨今重要なCO2吸収源として注目されている。昨年12月に都内で開催されたブルーカーボンをテーマにした「海藻活用シンポジウム」には、予定人数100人を超える約160人が参加した。北海道大学名誉教授で海藻活用研究会副会長を務める宮下和夫氏は「海藻活用によるブルーエコノミーの実現に向けて」と題して基調講演を行った。同氏は、「海藻は、ブルーカーボンとして優れた炭酸ガス固定能力を持つ。それを活用しながら、肥料や飼料、機能性食品素材としてさらに有効活用していくことが重要になる」と強調した。
ジャパンブルーエコノミー技術研究組合・理事長の桑江朝比呂氏は、同組合が2020年より始めた「Jブルークレジット®」制度の取り組みなどを報告。Jブルークレジットとは、ブルーカーボンを定量化して取引可能なクレジットとして活用する手法。CO2を吸収できる漁業者などがブルーカーボンクレジットを創出、削減できないCO2排出量を相殺したい企業や、団体が購入する仕組みで、運用から約5年、認証数は年々増えており、累計認証数は40件を超える。最近は、海藻養殖が増えているという。同氏は、「海藻は、カーボンの価値だけでなく、自然ベースで環境や社会全体を考えたプロジェクトとしてニーズが高く、購入者の価格に良い影響をもたらす」という。
会場には、海藻関連の食品、健康食品事業者なども参加しており、「県から説明があり、シンポジウムに参加した」「サプリメントを販売する中、SDGsの観点から興味がある」「中小企業では、藻場を測定するのにコストが掛かる。自治体のサポートがないとなかなか難しい」など、様々な声が聞かれた。具体的に取り組んでいる事業者も。フコイダンやメカブなどを使用した商品を販売する通販メーカーのヴェントゥーノ(福岡市中央区)は、2021年に福岡県内の糸島漁業協同組合とブルーカーボン協定を締結。昨秋に、糸島市と糸島漁業協同組合との産官民による「Jブルークレジット」構想を発表した。今後、連携強化を図り、産官民による福岡県初の同クレジットの認証取得を目指す。つづく
詳しくは健康産業新聞1803号(2025.1.1)で
健康産業新聞の定期購読申込はこちら